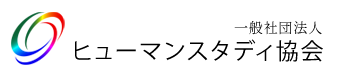※本サイトに掲載している写真・文面の無断流用は固くお断りいたします。
私は貴協会が指摘するところのある団体で学び、インストラクターの資格を取得しました。その後、この理論が増永先生のものと知り、これからどうやって伝えていけばいいかと悩んでいます。
まずは、当協会までご遠慮なくご相談ください。
当協会は、たとえどのようなルートで学んでしまったとしても、増永先生のご研究成果に感銘を受け、さらに学び、正しい立ち位置から伝えていきたいとお考えの方の受け皿となることを目的の一つとしています。
協会員となるための資格について教えてください。
「ご研究の尊厳を守る」という意味での簡単な審査はありますが、基本的に当協会の趣旨にご賛同いただき、増永先生のご研究についての基礎的な知識を学んでいただくことで、どなたでも協会員となる資格を得ることができます(すでに知識をお持ちの方は審査のみ)。当協会には「正会員」と「賛助会員」という資格があります。詳しくはお問合せください。
増永先生の研究成果をベースに自分なりの仮説検証をして、独自の理論を構築していくことは可能ですか?
はい。それが私たち協会員に課せられたテーマでもあります。
人生をかけて築き上げたご研究を後世に継承するにあたり、その足元にも及ばない知見しかもたない我々ができる役割は「原典の存在を残し続けること」。そして、そのうえで、この原典となる研究成果を活かせる機会をつくることだと考えています。
増永先生のご遺族からは、「これは完成された研究ではない」ということを協会員に伝えるようにと言われています。「これを原典として、ここからは自分たちで進みなさい」とも言われています。
ご研究の存在を明示し、敬意を払いつつ、自らの経験や知識、仮説検証などを加味することで、それぞれ発展させていける場が当協会の立ち位置であり、そのような意思を持つ方々の活動の裏付けとなる団体でありたいと考えております。
以前より、この理論の出所が「増永篤彦」という方とは聞いていましたが、私が学んだところでは、似たような研究をされていた人が別にいて、その理論を引き継いでいるから問題ないということでしたが…。
動物占い等、世に出回っている無断流用・無断改変者たちの偽りの系譜や都合の良い解釈に惑わされないために、三命方象こと増永篤彦先生の著書「生まれ日占星術」のまえがきに記載されている文章を以下に転載します。
【生まれ日占星術 個性学入門 63・64年版 まえがきより抜粋】
ところで、今年の春から、大阪と東京で別々のコンピュータソフト会社が、「生まれ日占星術」の盗作をしてソフト販売を始めた。それは、それなりに売れているようである。やむなく十五年の禁を破って、初めて個性学の著者としてその見解を発表することになったのである。
私はこの個性学、ないしはその母体である心理的な十二運(新推命学)は、昭和三十年頃からの研究であり、その思想と構成を、東京の人間科学研究所のH氏、降って昭和五十年代の日本占術協会のM氏が借用されている。こうしたことは、斯界の推命術の発展を思うために、あえて著作権としての有無を問うことはなかった。そしてまた、巷間の占術家が、実際に客に対して、私の「生まれ日占星術」のコピーや文章そのものを自分の研究の如く宣伝し、権威づけることも黙視していた。
しかし、世間のコンピュータ盲信による神秘化を利用した事業として、このようなコンピュータソフトを盗作することは、芸術上や思想上の倫理として、研究家としては、実に嘆かわしい次第である。しかしまた、このことは現代の四柱推命が、生まれ日による個性学を盗用する外には、人をうなずかせるだけの性格理論や法則が見当たらないことも物語っているといえる。
今日のところでは、その決着はついていないが、読者のために一応まえがきとして、提起した。
昭和六十二年十一月一日 三命方象こと 増永篤彦
この文面に記載されているH氏やコンピューターソフトを扱った会社、そこから派生した個人・団体等がどこの誰かは、このサイトにたどり着かれた方ならお分かりかと思います。
尚、このまえがきの文頭において、「個性学」という言葉が作られた時代背景ついても言及されています。そのうえで追記させていただくと、ある団体が1997/05/08に「個性學」という商標登録を行っていることも確認できます(特許庁商標検索https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0000)このような歴史的事実をどのように受け止めるのか、「人の性格」を学び、伝える方たちだからこそ、その良心が問われるのではないでしょうか?
ヒューマンスタディ協会が設立するに至った理由を教えてください。
すでに無断流用・無断改変が蔓延していたことは前出の通りです。
増永先生がご逝去されたのちには、ご遺族に対し、さまざまな人から「研究成果を売り渡して欲しい」との、接触を受けていたというお話も直接お聞きしています。
このような過去からも、ご遺族はご研究の行く末に不安を持たれていました。また、このような行為をしている個人・団体の数々が、真実を隠しながら商売を行い続け、その結果として被害者が増え続けていることにも深く心を痛めておられました。
そのため、ご研究の存在を世に残し続けることがこのような行為を防ぐための最善策になるとお考えになり、ご縁をいただいた当協会の設立メンバーがその役割をお受けすることとなりました(設立にあたっては、増永先生の秘書として長年お勤めになられていた方を紹介していただき、当協会の顧問となっていただきました)。
設立に至る経緯としての最後に、ご遺族の名誉を守るためにも協会として申し上げておくことがあります。
ご遺族がこの理論や著書の一部、または全てを過去に誰かに売り渡したことはありませんし、その流用についての許可や、それに伴う金銭の授受等を行ったことも一切ありません。それは故増永先生のご意志であり、そのような行為を、ご遺族は「研究を冒涜する行為である」と考えておられるからです。ですからもちろん、協会の設立時においても、また、当協会が「人の研究」を再発行する際にも、ご遺族との間に金銭授受の行為が発生したことは一切ありません。
増永先生の研究データは単に四柱推命の統計をとったものではないのですか?
前出のような個人や団体が、「これは占いではなく、統計学」という説明をされているようですが、それは正しくありません。「占いを統計学的検証で再構築した」と言ったほうが正しいでしょう。
それではどのような背景のもとで統計学的検証が行われたのでしょうか?
数千年の歴史と言われる四柱推命ですが、その長い歴史の中で誰一人として科学的検証(統計学的検証)を行った研究者はおらず、それゆえに、そのような文献も存在しませんでした。これは、日本に伝来し、いくつかの流派に分かれた後でさえも同じでした。
その理由の一つは、統計学自体が比較的新しい学問(18世紀頃に統計の基礎が築かれ、19世紀に広まる)であることに加え、増永先生以外に学者として占術に真摯に向き合う者が他にいなかったということ。
さらにもう一つの理由としては、これが一番の障害となりますが、四柱(年・月・日・時間)の一つの柱である「生まれた時間」という課題です。この一つの柱の情報が欠けていると四柱推命としての正確な判断が成り立たないからです。
しかし、現代においても生年月日は誰でも即答できるものの、母子手帳を見ずに生まれた時間までを即答できる人など、ほとんどいません。ましてや、明治、大正のころであれば、自分の「生まれた時間」を知るものなど、ほとんどおらず、そのような背景のもとで四柱推命として統計といえるだけのデータ数を臨床的に集めることは不可能だったからです。
では、増永先生はどのように統計をとられたのでしょうか?
統計は仮説を立てることから始まり、それが正しいか否かを検証することになります(この仮説の立て方というものがとても重要で、これは別途、他のQ&Aにて記載します)。
その仮説に基づき、統計と言えるだけの万単位のデータを集めるために、生まれた時間を除外し、生年月日のみで統計をとることになりました。
同じ生年月日となる人(当時の日本全国で数百人~千数百人)が皆すべて同じ性格であるはずはないが、なんらかの共通となる傾向性をもっていて、その傾向性が60周期においても再現されつづけるか否か、という検証を行ったのです。
その統計データを60類型として(男女別で120類型)でまとめ上げられたのが「生まれ日占星術(個性学入門)」なのです。
つまり、四柱推命をベースとはしているものの、従来の考え方で導きさされる四柱推命の統計データではないということなのです。
四柱推命として伝えることに問題はありますか?
以下の記述をご覧いただければ、四柱推命を学ばれたからと言って、増永先生の研究データを無断で利用することにも無理があることに気付いていただけると思います。
干支という六十の構造は、実は五行思想より前に完成されたものであるから、干支の実態は、その前に先行したとみられる四行思想を根本としている、という見方の方が本当はただしくはないかということが、私の最初からの研究テーマであった。
六十干支そのものは五行よりも四行的な思想を母体とするために、干支を原始的な干(五行)と支(十二支)との関係に分解するのではなく、六十の干支そのものの分子的なまとまり(丙寅なら丙と寅に分解せず、丙寅とまとまったものとしてみる)として考えるということが根本である。
個性学は、従来の思想では解けないこうした発想から、干と支の原始的な組合せを否定して、六十干支そのものを個性として考えたのである。その法則を詳述する暇はないが、実は、個性学は、四行思想のもう一歩手前の三行思想と二行思想を心理学的に構成させたものである。したがって、従来の干と支の関係による五行思想的な立場では、私の六十干支による個性の解明は不可能である。
上記の記述も「生まれ日占星術・個性学入門」に書かれているものです。
前提としての仮説が違えば、その後の論理展開や推論、そして結論も異なる結果になります。前提のない結論(前提がわからない結論)という使い方で伝えることは避けられたほうがよろしいかと思います。